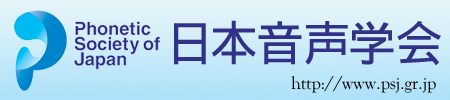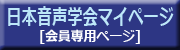組織
第17代[現在]:2025(令和7)年4月~2028(令和10)年3月
役員
| 会長 | 斎藤弘子 |
| 理事 | 田嶋圭一 |
| 林良子 | |
| 白勢彩子 | |
| 米山聖子 | |
| 五十嵐陽介 | |
| 前川喜久雄 | |
| 宇都木昭 | |
| 田中真一 |
委員会
庶務委員会
| 委員長 | 米山聖子 |
| 副委員長 | |
| 委員 | 白勢彩子、植田尚樹、山崎亜希子 |
| 委員長挨拶 | この度,白勢彩子先生から引き継ぎ,庶務委員長を拝命いたしました。今期の庶務委員は,白勢彩子先生,植田尚樹先生,山崎亜希子先生にお願いしております。この体制で,斎藤弘子会長を補佐し,円滑な学会運営を心がけていきたいと考えております。会員の皆様にはご指導を賜りますようお願い申し上げます。前任の白勢庶務委員長のもと,庶務委員会の業務内容は大幅にスリム化されました。今期の庶務委員会もその方向性を引き継ぎ,引き続き円滑な学会運営を目指してまいります。また,近年は学会員の高齢化と会員数の減少が進んでおり,今後も難しい学会運営が求められることが予想されます。業務の効率化とさらなるスリム化を進め,学会の発展に尽力してまいりますので,会員の皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。今後の3 年間,どうぞよろしくお願い申し上げます。 |
編集委員会
| 委員長 | 五十嵐陽介 |
| 副委員長 | |
| 委員 | 籠宮隆之、松浦年男、高田三枝子、髙橋康徳、竹安大 |
| 委員長挨拶 | このたび,田嶋圭一先生の後任として,編集委員長を拝命いたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 前期では,査読の公平性と中立性を維持し,編集作業を円滑に進めるため,編集委員は編集業務に専念し,査読は編集委員が適任者に依頼する体制が構築されました。この方針を今期も継承し,より充実した運営を目指してまいります。 査読制度にはさまざまな課題が指摘されていますが,学術論文の質を担保する仕組みとして,依然として最も有効なシステムであることに変わりはありません。加えて,査読は学術研究の発展において,専門家同士の対話の場としても重要な役割を果たし続けるでしょう。『音声研究』に投稿される論文は多岐にわたり,それぞれの分野に固有の慣習や文化が存在しています。私自身,これまで編集委員を務める中で,査読報告書の書き方や,それに対する応答の仕方にも多様なスタイルがあり,時にはそれが投稿者と査読者の対話を妨げることがあると感じてきました。『音声研究』の編集に携わる者として,さらには学術研究一般における査読プロセスの在り方についても,よりよい方法を模索し,提案していくことが編集委員会の重要な役割の一つであると考えています。 これまでと同様に,査読の公平性と中立性を維持し,編集作業の円滑な運営に努めてまいります。皆様のご支援とご協力を賜りますよう,何卒よろしくお願い申し上げます。 |
企画委員会
| 委員長 | 田中真一 |
| 副委員長 | 松井理直 |
| 委員 | アヴェ・エリーヌ、生駒美喜、植田尚樹、木村琢也、熊谷学而、佐野真一郎、杉本淳子、須藤潤、高山知明、竹内はるか、竹村亜紀子、竹安大、那須昭夫、ハン・ヒソン、平山真奈美、黄竹佑、ホアン・ヒョンギョン、守本真帆 |
| 委員長挨拶 | 企画委員会は,全国大会(9月)と研究例会(6月,12 月)の企画運営をおもに担当します。コロナ禍を経て,それらの開催形式にもバリエーションが見られるようになりました。前委員会から継続して,対面とオンラインそれぞれの良さを活かしながら,多くの方が満足して参加できる会になるよう工夫するつもりです。 他学会と同様,本学会も発表者そして会員の減少が問題となってきています。国際交流委員会,音声学普及委員会など他の委員会と連携しながら,とくに学生をはじめとする新規参加者の獲得を目指します。魅力的な企画とともに,会員が参加・発表しやすい場の提供を工夫し,多くの方が本学会に継続して関わる環境を委員会として作っていきたいと思います。 よく言われるように,音声学はさまざまな学問領域と接点を持ちます。それらの領域から新規参加者を取り込む可能性があるわけです。全国大会・研究例会が,参加者の専門,年齢,所属といった背景の違いを超え,一層,建設的な議論ができる魅力的な場になるよう取り組みます。企画についてご意見をお寄せいただくとともに,ご協力のほどお願いいたします。 |
広報委員会
| 委員長 | 宇都木昭 |
| 副委員長 | 安啓一 |
| 委員 | 大井川朋彦、守本真帆、渡丸嘉菜子、向井洋一、梁辰 |
| 委員長挨拶 | 2025 年4月より3年間,広報委員長を務めさせていただくことになりました。広報委員会のこれまでの主要な業務は,学会ホームページと会員向けメール配信のかたちでの各種の情報発信でした。今後もこれらの業務を引き継ぎ,円滑に進めていきたいと存じます。 私個人的には,これまで様々な研究・教育機関に身をおく中で,所属する場によって各種の情報が入りやすいところもあれば入りにくいところもあるということを実感してきました。学問におけるそういった情報の格差を縮めることは,学会の重要な使命の一つだと感じており,この点で広報委員会の担う役割は大きいと感じています。 一方で,多くの教育・研究機関において教員・研究者の業務が増しがちな昨今の状況において,学会を持続可能なかたちで運営していくためには,委員会業務のスリム化を常に念頭においておかなければならないとも考えています。業務の意義や効果の優先度に応じて業務を減らすことを意識しつつ,時代の変化に伴って新たな試みが求められるような局面に対しては積極的に対応できるよう,心がけていきたいと思います。 委員の皆様のご協力を仰ぎつつ,また,広く学会の内外の方々の意見に耳を傾けながら,委員会業務を進めていく所存です。皆様のご協力,ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。 |
国際交流委員会
| 委員長 | 田嶋圭一 |
| 副委員長 | 菅原真理子 |
| 委員 | 平山真奈美、黄竹佑、溝口愛、篠原靖明、鮮于媚 |
| 委員長挨拶 | このたび,国際交流委員長を拝命いたしました。まずは,これまで本委員会の発展に尽力されてこられた前任の近藤眞理子委員長をはじめ,関係者の皆様に心より感謝申し上げます。 これまで国際交流委員会では,海外研究者による講演を積極的に企画・開催してまいりました。近年,オンライン形式での学会や講演会が普及したことで,地理的な制約を超えて多様な研究者をお招きできるようになり,多くの貴重な講演の機会を得ることができました。今後もオンライン講演の利点を最大限に生かし,充実した講演会を企画してまいりたいと考えております。「この研究者の講演を聞きたい」といったご要望がございましたら,ぜひ国際交流委員にお知らせください。 一方で,対面での講演会にはオンライン講演では得られない大きな魅力があることも事実です。休憩時間や懇親会での交流や意見交換は,特に若手研究者にとって貴重な人脈作りの機会となり,また,新たなアイデアや共同研究のきっかけにもなる可能性があります。当然,財政的な問題は最大のハードルとなりますが,実現に向けて可能な限り努力してまいります。会員の皆様におかれましても,海外研究者を日本に招聘する機会がございましたら,ぜひお知らせいただければ幸いです。 国際交流のさらなる発展のため,皆様のご支援とご協力を賜りますよう,何卒よろしくお願い申し上げます。 |
会則検討委員会
| 委員長 | 白勢彩子 |
| 副委員長 | 荒井隆行 |
| 委員 | 高田三枝子、加藤大鶴 |
| 委員長挨拶 | 大東文化大学の米山聖子先生から引き継いで,会則検討委員会の委員長を務めることとなりました。本学会は100周年という大きな節目を迎えます。100年という歴史を背負いながら学会を持続可能なものとしていくには,会員が参加しやすい,有意義な集まりとなっていることが肝要なのではないでしょうか。学会趣旨の一つにも「会員相互の連絡提携を図ること」とあります。これを支えるものとして,会則があると捉えています。これまでの会則検討委員会の提案を踏まえつつ,より会則を整備していきたいと考えております。どうぞ,ご理解,ご協力のほど,よろしくお願い申しあげます。 |
音声学普及委員会
| 委員長 | 林良子 |
| 副委員長 | 金村久美 |
| 委員 | 牧野武彦、内田洋子、磯村一弘、木下直子、松田真希子、木元めぐみ、安田麗、阿栄娜、孫静、王可心 |
| 委員長挨拶 | このたび,田中真一先生の後を受けて,2 度目の音声学普及委員長を拝命いたしました。1 度目の平成28年度就任時には,音声学普及委員会は生まれて日も浅く,当時大きな問題となっておりました会員の急激な減少に歯止めをかけるべく,様々な入門講座,セミナー等を試行錯誤して開催してまいりました。しかし,それ以来,会員の皆様,理事の皆様のご尽力のもと,特に英語音声学,日本語教育音声学の分野において,会員以外の方々にも音声学を広く普及する地盤が十分に築かれてきたと思います。 昨今では,音声・音声教育研究をめぐる社会的状況も,音声翻訳システム,合成音声使用の一般化など動的に変化しつつあります。今後は,会員のニーズや,研究の社会的還元,収益化も念頭に入れて,講座やセミナー内容に刷新を図りつつ,風通しの良い本学会の特性を活かしながら魅力的な催しを企画していきたいと思います。皆様,どうぞよろしくお願い申し上げます。 |
100周年記念事業委員会
| 委員長 | 前川喜久雄 |
| 副委員長 | 北原真冬 |
| 委員 | 松井理直、大井川朋彦、榊原健一、渡丸嘉菜子、横江百合子、近藤眞理子 |
| 委員長挨拶 | 2019年に会長をお引き受けした際,本欄の挨拶に「これを最後のご奉公と考えて」云々と書きましたが,学会役員の70歳定年制に照らしてぎりぎり任期が残っており,今回,100周年記念事業委員長をお引き受けすることになりました。任期中の2026年が学会創立百周年にあたりますので,種々の記念事業の企画が今期の中心的な仕事になるでしょう。学会の古株がお引き受けするにはふさわしい仕事かと感じている次第です。幸い,前委員会が北原委員長の指導よろしきを得て準備を進めてこられたようですので,これからきちんと引継ぎを行い,斎藤会長とも相談しながら,着々と準備を進めたいと思います。学会の財政を考慮しつつ,会員のみなさまにとって実のあるイベントを立案したいと考えております。小さな学会のこととて,みなさまにはいろいろと協力をお願いすることがあろうかと思います。その折は,何卒よろしくお願いいたします。 |
評議員
|
会計監査
|
顧問
|