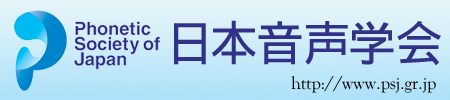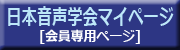3rd ICPPが、2013年12月20~22日に国立国語研究所(東京都立川市)で開催されます。詳しくは以下のページをご参照ください。
http://www.ninjal.ac.jp/phonology/IntlConference/3rd_icpp/home/
現在、3rd ICPPの参加申込を行っております。参加希望の方は、以下のページをご参照の上、
icpp3[at]ninjal.ac.jpまでお申し込み下さい。
http://www.ninjal.ac.jp/phonology/IntlConference/3rd_icpp/registration/
‘その他の催し’ カテゴリーのアーカイブ
日本行動計量学会第41回大会開催のお知らせ
重ねてのご案内になるかと思いますが、下記の通り、日本行動計量学会第41回大会を開催いたします。プログラムは、大会Webサイトをご覧ください。
非会員の方でも、当日、大会受付にて、入会申込をしていただきますと、入会手続き中として、会員扱いでの参加が可能です。ぜひとも、ご検討ください。もちろん、非会員の方のご参加も歓迎いたします。
本大会が有意義な会となるよう実行委員一同最善を尽くし、皆様をお待ちしております。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
○大会開催要項
会期:2013年9月3日(火)~6日(金)(9/3はチュートリアルセミナー)
会場:東邦大学習志野キャンパス(千葉県船橋市三山2-2-1)
大会実行委員長:菊地賢一(東邦大学理学部)
大会Webサイト:http://bsj.wdc-jp.com/2013/
○大会参加申込
「各種申込について」
http://bsj.wdc-jp.com/2013/application/
をご覧いただき、全体的な手順をお確かめの上、お申し込みください。
○公開講座(第41回大会の特別講演として、次の公開講座を実施します)
日時:2013年9月5日(木)15:00~17:00
場所:東邦大学習志野キャンパス(薬学部C館1階C-101講義室)
共催:東邦大学理学部
タイトル:サッカーにおけるデータ分析-サッカーの現場における分析力とは?-
講演予定者:
大熊清氏(FC東京 テクニカルダイレクター・南アフリカワールドカップ日本代表コーチ)
湯浅理平氏(公益財団法人 日本サッカー協会 代表チーム テクニカル アナリスト)
澁川賢一氏(東邦大学理学部専任講師・元Jリーグ フィジカルコーチ)
概要:
サッカーにおけるスカウティングとは、どのようなものなのか。データ収集と分析は、どのように行われるのか。そして、その分析結果が、どのように現場にフィードバックされ、チーム全体としての戦術や選手個々のプレー、パフォーマンスに生かされるのか。コーチング、スカウティング、フィジカルコンディショニングの専門家の立場からお話いただきます。
(※東邦大学理学部公開講座としても開催されます。大会参加者だけではなく、どなたでも無料で聴講可能です。公開講座は参加申込の必要はありません)
○お問い合わせ先
参加登録などWebでの手続き関係
大会ヘルプデスク bsj-desk@bunken.co.jp
大会全般の問い合わせ
第41回大会実行委員会 bsj2013@toho-u.ac.jp
2013年8月5日
大会実行委員長
菊地賢一(東邦大学理学部)
非会員の方でも、当日、大会受付にて、入会申込をしていただきますと、入会手続き中として、会員扱いでの参加が可能です。ぜひとも、ご検討ください。もちろん、非会員の方のご参加も歓迎いたします。
本大会が有意義な会となるよう実行委員一同最善を尽くし、皆様をお待ちしております。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
○大会開催要項
会期:2013年9月3日(火)~6日(金)(9/3はチュートリアルセミナー)
会場:東邦大学習志野キャンパス(千葉県船橋市三山2-2-1)
大会実行委員長:菊地賢一(東邦大学理学部)
大会Webサイト:http://bsj.wdc-jp.com/2013/
○大会参加申込
「各種申込について」
http://bsj.wdc-jp.com/2013/application/
をご覧いただき、全体的な手順をお確かめの上、お申し込みください。
○公開講座(第41回大会の特別講演として、次の公開講座を実施します)
日時:2013年9月5日(木)15:00~17:00
場所:東邦大学習志野キャンパス(薬学部C館1階C-101講義室)
共催:東邦大学理学部
タイトル:サッカーにおけるデータ分析-サッカーの現場における分析力とは?-
講演予定者:
大熊清氏(FC東京 テクニカルダイレクター・南アフリカワールドカップ日本代表コーチ)
湯浅理平氏(公益財団法人 日本サッカー協会 代表チーム テクニカル アナリスト)
澁川賢一氏(東邦大学理学部専任講師・元Jリーグ フィジカルコーチ)
概要:
サッカーにおけるスカウティングとは、どのようなものなのか。データ収集と分析は、どのように行われるのか。そして、その分析結果が、どのように現場にフィードバックされ、チーム全体としての戦術や選手個々のプレー、パフォーマンスに生かされるのか。コーチング、スカウティング、フィジカルコンディショニングの専門家の立場からお話いただきます。
(※東邦大学理学部公開講座としても開催されます。大会参加者だけではなく、どなたでも無料で聴講可能です。公開講座は参加申込の必要はありません)
○お問い合わせ先
参加登録などWebでの手続き関係
大会ヘルプデスク bsj-desk@bunken.co.jp
大会全般の問い合わせ
第41回大会実行委員会 bsj2013@toho-u.ac.jp
2013年8月5日
大会実行委員長
菊地賢一(東邦大学理学部)
言語学系学会連合主催のイベントのお知らせ
第3回 ことばカフェ
- テーマ:
発見と成長をはぐくむ異文化との出会い
―異文化の人たちとのコミュニケー ションを語り合おう― - 日時: 2013年8月3日 (土) 14:00~17:00 (開場:13:30)
- 場所: サロンド冨山房Folio,東京都千代田区神田神保町1-3 冨山房ビルB1
- 講師: 井上優(麗澤大学),大山全代(Movement for Language and Culture, New York)
- 司会・企画: 三宅和子(東洋大学)
- 参加費:無料
- 公式サイト: https://sites.google.com/site/kotobacafeuals/
- 参加方法
- どなたでも参加できます。
メールの事前申し込みで定員(先着50名)になり次第、受付を終了します。 - ことばカフェ参加申込み、連絡先:
uals.cafe@gmail.com(言語系学会連合事務局)
- どなたでも参加できます。
日本コミュニケーション障害学会「第39回学術講演会」のお知らせ
下記の通り、日本コミュニケーション障害学会「第39回学術講演会」が開催されます。
今回の学会テーマは「生きる、伝えあう ~ことばを紡ぐ、こころを織りなす、いのちをつなぐ」です。音声コミュニケーションに関する一般演題の他、教育講演、モーニングセミナー、シンポジウムなども企画されています。特に、シンポジウム2では「これって本当に構音障害?」が開催されます。多くの皆様の参加をお待ちしております。
※会場が上智大学に変更になりました。詳しくは、以下のページをご覧ください。
今回の学会テーマは「生きる、伝えあう ~ことばを紡ぐ、こころを織りなす、いのちをつなぐ」です。音声コミュニケーションに関する一般演題の他、教育講演、モーニングセミナー、シンポジウムなども企画されています。特に、シンポジウム2では「これって本当に構音障害?」が開催されます。多くの皆様の参加をお待ちしております。
※会場が上智大学に変更になりました。詳しくは、以下のページをご覧ください。
- 期日:2013年7月20日(土)、21日(日)
- 会場:上智大学 四谷キャンパス(★変更になりました)
- 会長:進藤美津子(上智大学言語聴覚研究センター)
- URL:http://jacd39.umin.jp/
日本音響学会第130回技術講習会 「Praatによる音声加工と知覚実験の実施法」講習会
日本音声学会は平成25年10月31日,11月1日に開催される日本音響学会第130回技術講習会「Praat による音声加工と知覚実験の実施法」講習会を協賛します。
日本音声学会会員は,協賛学会員価格(30,000円)で参加することができます。ただし,学生会員は一般学生価格(8,000円)となります。(詳細は下記のURLをご確認ください。)
日本音声学会会員は,協賛学会員価格(30,000円)で参加することができます。ただし,学生会員は一般学生価格(8,000円)となります。(詳細は下記のURLをご確認ください。)
- 申込方法:
下記のURL(日本音響学会のサイト)より申込用紙をダウンロードし,所定の事項を記入の上,日本音響学会までファクシミリ又は郵送でお申し込み下さい。(申込書のページをそのままご送付下さい。)
http://www.asj.gr.jp/lecture/2013/seminar20131031.pdf - 申込先:
日本音響学会事務局 〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-18-20
ナカウラ第5ビル2階
Tel. 03-5256-1020
Fax. 03-5256-1022
音韻論フォーラム2013における講演会(日本音韻論学会より)
8月21日-23日の日程で,音韻論フォーラム2013が札幌学院大学(札幌市)にて開催されます。研究発表を希望される方は6月30日までにご応募ください。また,Michael Hammond氏(アリゾナ大学)とBert Botma氏
(ライデン大学)の講演会につきましては,音声学会の会員であれば,無料でご参加いただけます(講演会以外の部分は,音韻論学会会員なら一般1000円,学生500円,非会員2000円)。連絡先や日程やプログラムなど,詳しくはこちら(http://sils.shoin.ac.jp/PhonWeb/)をご覧ください。
The 3rd International Conference on Phonetics and Phonology
The 3rd International Conference on Phonetics and Phonology (3rd ICPP)が、2013年12月20~22日に国立国語研究所(東京都立川市)で開催されます。
現在、ポスター発表を募集しております。発表の応募締切は2013年8月31日です。詳細については、icpp3@ninjal.ac.jpまでお問い合わせください。
現在、ポスター発表を募集しております。発表の応募締切は2013年8月31日です。詳細については、icpp3@ninjal.ac.jpまでお問い合わせください。
- Date: December 20-22, 2013
- Place: National Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL)
- Website: http://www.ninjal.ac.jp/phonology/InternationalConference/3rd_icpp/home/
- Contact: icpp3[at]ninjal.ac.jp
日本行動計量学会第41回大会開催のお知らせ
下記の通り、日本行動計量学会第41回大会を開催いたします。すでに、各種申込の受付を開始しております。大会までに当学会に入会の申し込みをしていただきますと、入会手続き中として、会員扱いでの発表、参加が可能です。ぜひとも、ご検討ください。もちろん、非会員の方のご参加も歓迎いたします。
本大会が有意義な会となるよう実行委員一同最善を尽くし、皆様をお待ちしております。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
○大会開催要項
会期:2013年9月3日(火)~6日(金)(9/3はチュートリアルセミナー)
会場:東邦大学習志野キャンパス(千葉県船橋市三山2-2-1)
大会実行委員長:菊地賢一(東邦大学理学部)
大会Webサイト:http://bsj.wdc-jp.com/2013/
○各種日程
3月 1日(金) 特別セッションの企画募集開始
4月 1日(月) 一般研究発表・事前参加申し込みなど各種申込開始
4月30日(火) 特別セッションの企画募集締切
6月 7日(金) 一般研究発表申込締切
6月21日(金) 抄録原稿提出締切
8月16日(金) 事前参加申込・参加費入金締切
○各種申込
大会Webサイトの「各種申込について」
http://bsj.wdc-jp.com/2013/application/
をご覧いただき、全体的な手順をお確かめの上、お申し込みください。
○チュートリアルセミナー
日時:2013年9月3日(火)13:00~17:00(予定)
場所:東邦大学習志野キャンパス
講師:杉澤武俊先生(新潟大学)
定員:50名
タイトル:マルチレベルモデリング入門
概要:
行動計量研究では、二段(多段)抽出データや個人内の反復測定データなど、個人が集団にネストされた、あるいは、複数時点の測定値が個人にネストされた階層構造を持つデータを扱うことも多い。階層構造を持つデータに対しては、従来の単純無作為抽出を前提とした推定・検定ではなく、階層構造を考慮した手法の適用が要求される。マルチレベルモデリングはそのようなデータの階層構造をモデルに組み込んだ分析手法である。本チュートリアルセミナーでは、マルチレベルモデリングをこれから学ぼうという人を念頭に、回帰分析程度の知識を前提として、マルチレベルモデリングの基本的な考え方や実際の分析手順を、フリーソフトウエアのRを使った分析方法などにも触れながら解説を行う。(※パソコンの設置してある実習室で、Rを使った実習も行う予定です)
○公開講座(第41回大会の特別講演として、次の公開講座を実施します)
日時:2013年9月5日(木)15:00~17:00(予定)
場所:東邦大学習志野キャンパス
共催:東邦大学理学部
タイトル:サッカーにおけるデータ分析(仮)
講演予定者:
大熊清氏(FC東京育成部テクニカルダイレクター)
湯浅理平氏(日本サッカー協会 代表チーム テクニカル アナリスト)
概要:
サッカーにおけるスカウンティングとは、どのようなものなのか。データ分析は、どのように行われるのか。分析のポイントなどをご講演いただきます。
(※東邦大学理学部公開講座としても開催されます。大会参加者だけではなく、どなたでも無料で聴講可能です)
○お問い合わせ先
参加登録、抄録提出など、Webでの手続き関係
大会ヘルプデスク bsj-desk[at]bunken.co.jp
大会全般の問い合わせ
第41回大会実行委員会 bsj2013[at]toho-u.ac.jp
2013年4月1日
大会実行委員長
菊地賢一(東邦大学理学部)
本大会が有意義な会となるよう実行委員一同最善を尽くし、皆様をお待ちしております。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
○大会開催要項
会期:2013年9月3日(火)~6日(金)(9/3はチュートリアルセミナー)
会場:東邦大学習志野キャンパス(千葉県船橋市三山2-2-1)
大会実行委員長:菊地賢一(東邦大学理学部)
大会Webサイト:http://bsj.wdc-jp.com/2013/
○各種日程
3月 1日(金) 特別セッションの企画募集開始
4月 1日(月) 一般研究発表・事前参加申し込みなど各種申込開始
4月30日(火) 特別セッションの企画募集締切
6月 7日(金) 一般研究発表申込締切
6月21日(金) 抄録原稿提出締切
8月16日(金) 事前参加申込・参加費入金締切
○各種申込
大会Webサイトの「各種申込について」
http://bsj.wdc-jp.com/2013/application/
をご覧いただき、全体的な手順をお確かめの上、お申し込みください。
○チュートリアルセミナー
日時:2013年9月3日(火)13:00~17:00(予定)
場所:東邦大学習志野キャンパス
講師:杉澤武俊先生(新潟大学)
定員:50名
タイトル:マルチレベルモデリング入門
概要:
行動計量研究では、二段(多段)抽出データや個人内の反復測定データなど、個人が集団にネストされた、あるいは、複数時点の測定値が個人にネストされた階層構造を持つデータを扱うことも多い。階層構造を持つデータに対しては、従来の単純無作為抽出を前提とした推定・検定ではなく、階層構造を考慮した手法の適用が要求される。マルチレベルモデリングはそのようなデータの階層構造をモデルに組み込んだ分析手法である。本チュートリアルセミナーでは、マルチレベルモデリングをこれから学ぼうという人を念頭に、回帰分析程度の知識を前提として、マルチレベルモデリングの基本的な考え方や実際の分析手順を、フリーソフトウエアのRを使った分析方法などにも触れながら解説を行う。(※パソコンの設置してある実習室で、Rを使った実習も行う予定です)
○公開講座(第41回大会の特別講演として、次の公開講座を実施します)
日時:2013年9月5日(木)15:00~17:00(予定)
場所:東邦大学習志野キャンパス
共催:東邦大学理学部
タイトル:サッカーにおけるデータ分析(仮)
講演予定者:
大熊清氏(FC東京育成部テクニカルダイレクター)
湯浅理平氏(日本サッカー協会 代表チーム テクニカル アナリスト)
概要:
サッカーにおけるスカウンティングとは、どのようなものなのか。データ分析は、どのように行われるのか。分析のポイントなどをご講演いただきます。
(※東邦大学理学部公開講座としても開催されます。大会参加者だけではなく、どなたでも無料で聴講可能です)
○お問い合わせ先
参加登録、抄録提出など、Webでの手続き関係
大会ヘルプデスク bsj-desk[at]bunken.co.jp
大会全般の問い合わせ
第41回大会実行委員会 bsj2013[at]toho-u.ac.jp
2013年4月1日
大会実行委員長
菊地賢一(東邦大学理学部)
ICPP 2013 (NINJAL International Conference on Phonetics and Phonology 2013)
ICPP 2013が、2013年1月25-27日に、国立国語研究所(東京都立川市)で開催されます。
詳しくは以下のページをご参照ください。
http://www.ninjal.ac.jp/phonology/InternationalConference/icpp_2013/home/
まだ参加申込を受け付けておりますので、以下のページをご参照の上、
ICPP2013[at]ninjal.ac.jp までお申込下さい。
http://www.ninjal.ac.jp/phonology/InternationalConference/icpp_2013/registration/
詳しくは以下のページをご参照ください。
http://www.ninjal.ac.jp/phonology/InternationalConference/icpp_2013/home/
まだ参加申込を受け付けておりますので、以下のページをご参照の上、
ICPP2013[at]ninjal.ac.jp までお申込下さい。
http://www.ninjal.ac.jp/phonology/InternationalConference/icpp_2013/registration/
第29回NINJALコロキアム
- 講師:Larry Hyman (UC Berkeley)
- 演題:Why There Is No Canonical Pitch-accent System
- 日時:2013年1月24日(木)15:30-17:00
- 場所:国立国語研究所(東京都立川市)
- HP:http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/colloquium/#colloquium-top